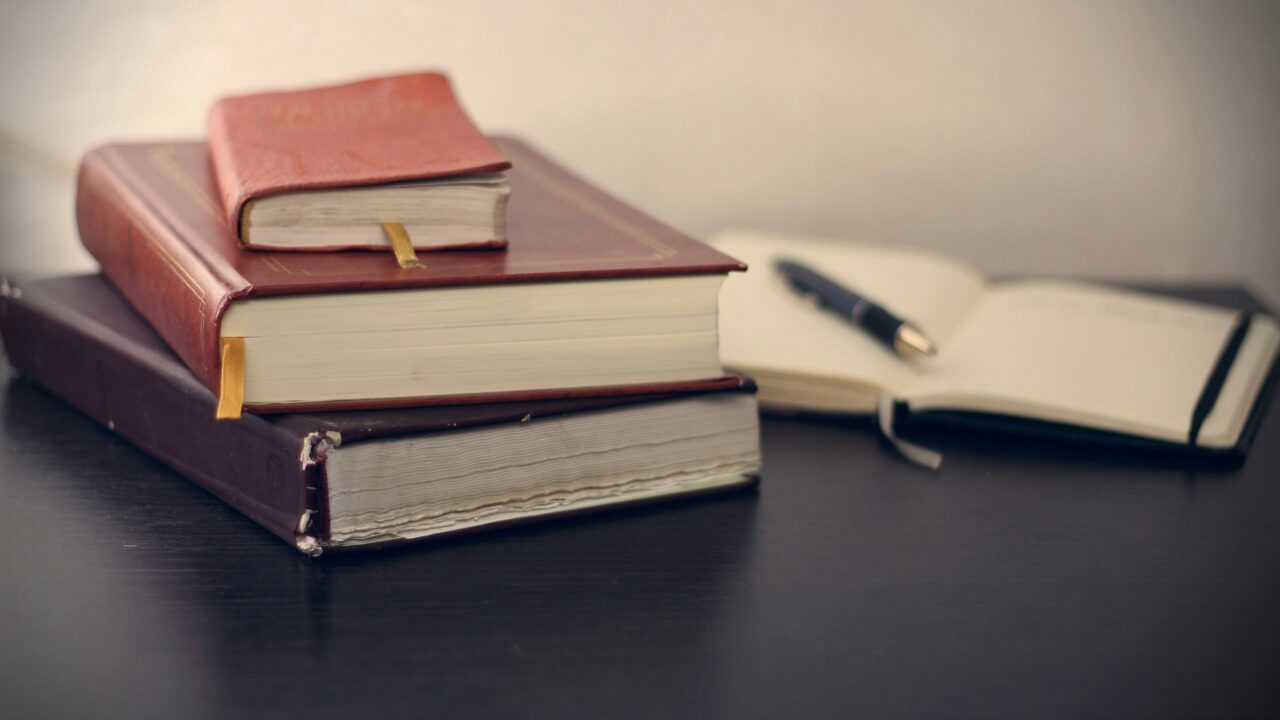化粧品や健康食品の広告で「この表現は薬機法違反にならないか?」と心配になることはありませんか。
薬機法のNGワードを知らずに使うと、最大2年の懲役や売上の4.5%の課徴金といった重い罰則が科され、企業の信用も失ってしまいます。
本記事では薬機法の基礎知識から代表的なNGワード、具体的な言い換え表現、違反を避ける3つの実践的なコツまで徹底解説します。
この記事を読めば、薬機法を守った安全な広告表現が身につき、安心して商品のPRができるでしょう。
薬機法とは健康被害の発生と拡大を防ぐための法律のこと
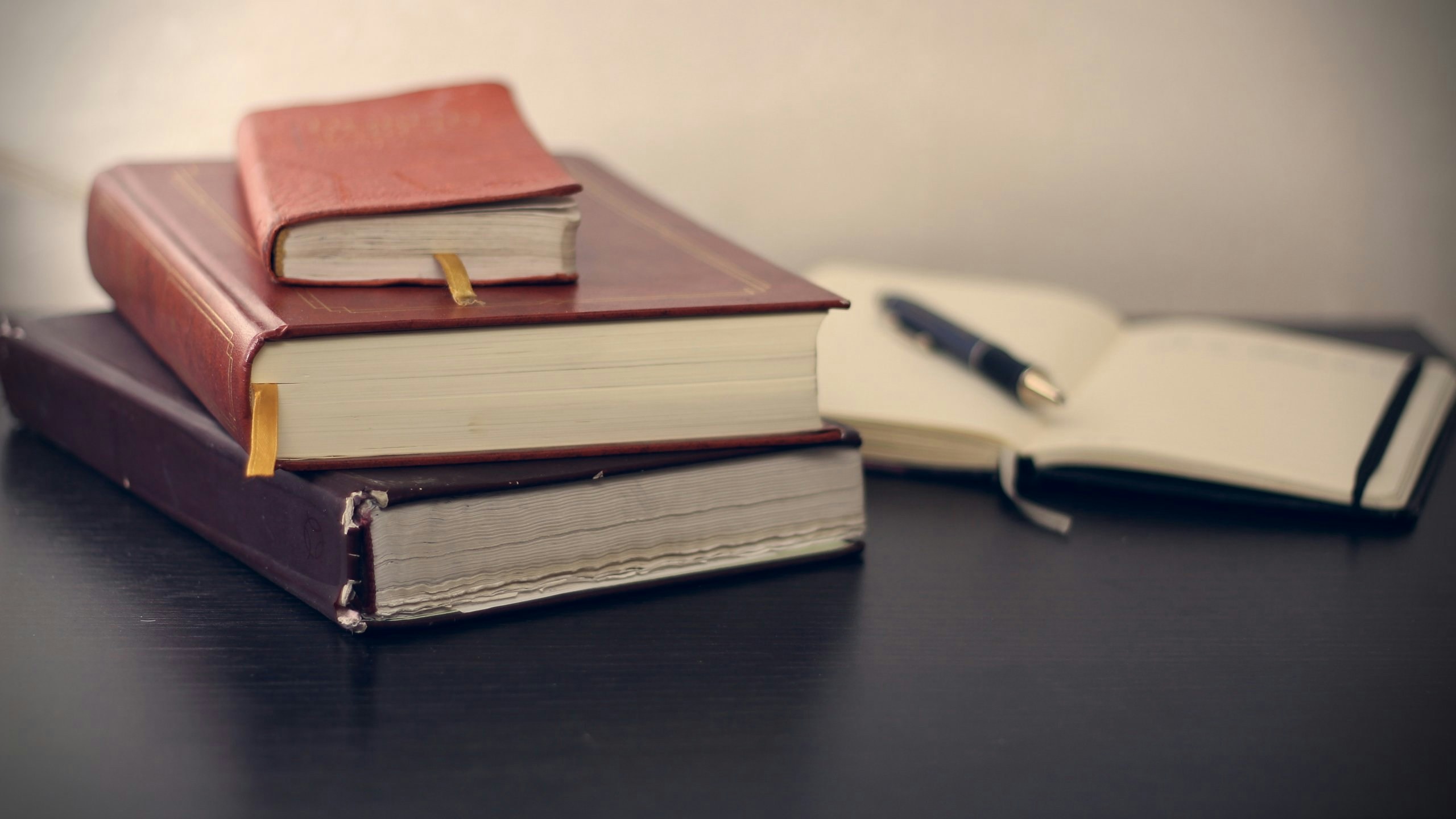
薬機法は医薬品や化粧品などによる健康被害を防ぐための重要な法律です。
規制対象や目的、違反時の罰則について詳しく解説します。
薬機法の規制対象
薬機法の規制対象は以下の5つです。
・医薬品(風邪薬や処方薬など)
・医薬部外品(育毛剤や制汗剤など)
・化粧品(ファンデーションやシャンプーなど)
・医療機器(体温計やMRIスキャナーなど)
・再生医療等製品(幹細胞治療用製品など)
健康食品やサプリメントは直接の規制対象ではありませんが、医薬品と誤認させる表現を使用すると薬機法違反です。
ただし、特定保健用食品や機能性表示食品などの国が認可した商品では、承認された範囲内で効果効能を表示できます。
薬機法の目的
薬機法は、医薬品などの品質・有効性・安全性の確保と、保健衛生上の危害の発生および拡大防止を主な目的としています。
製造から販売まで全てのプロセスを規制し、消費者が安心して使用できる製品を提供するのが狙いです。
広告表現では、誤解を招く表現や過剰な効果を謳うことを厳しく制限しています。
特に化粧品や健康食品などの分野では、医薬品との区別をハッキリさせて誤った商品を選ばないよう手助けする役割を果たしています。
医療上必要性が高い製品の研究開発促進も目的の一つとして掲げられており、保健衛生の向上を図っています。
薬機法違反の罰則
薬機法違反には以下の3つの重い罰則が設けられています。
刑事罰では、虚偽・誇大広告により2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科される可能性があります。
行政処分では、業務の停止命令や許可の取り消しなどが実施されます。
課徴金納付命令とは、2021年に新たに導入された制度で、違反期間中の対象商品売上の4.5%を納付しなければなりません(課徴金額が225万円未満は免除)。
処罰は単独ではなく併科される場合もあります。
違反の事実が公表されれば企業の社会的信用を損なうことになるでしょう。
ブランドのイメージダウンや取引先との関係悪化などの重大なリスクを避けるため、適切な表現に注意を払う必要があります。
薬機法で注意すべき4つのNGワード

薬機法違反を避けるため、特に注意が必要な4つの代表的NGワードを具体例とともに詳しく解説します。
1.安心・安全性を保証する
「安心」「安全」の表現は、医学薬学上認められた範囲を超えるため薬機法で規制されています。
「○○成分なので敏感肌の方でも安心です」「当商品の安全性は証明されています」といった表現は、消費者に誤解を与える可能性がありますよね。
「○○を使用すれば老後も安心」といった将来が保証されたかのような表現も禁止されています。
製品の安全性や効果には個人差があるので、絶対的な保証を示す言葉の使用は避けましょう。
安心や安全性に関する表現を使用した場合、行政処分や課徴金の対象となる可能性が高いです。
2.治る・治癒する
「治る」「治癒する」といった医療効果を示す表現は、薬機法で厳しく禁止されているNGワードです。
「あせもが治る」「○○病を治癒できる」などの表現を使用すると、行政指導だけでなく2年以下の懲役や200万円以下の罰金といった刑事罰の対象です。
過去には認められた範囲を超えた表現により処分を受けた事例も存在しており、絶対に避けるべき表現です。
医薬品でない限り、病気や症状の治療効果を謳うことは一切認められていません。
健康食品や化粧品において、治療に関する表現を使うと薬機法違反になるため細心の注意が必要です。
3.効能・効果がある
「効果」「効果的」の表現は、商品の効能効果の程度が人によって異なるため薬機法違反です。
「ダイエットに効果的」「便秘予防に効果があります」といった特定の症状や問題への効果を断定する表現は、消費者の誤解を招く可能性があります。
同じ商品を使用しても個人の体質や生活習慣により結果は大きく変わるため、効果を保証するような表現は誇大広告と見なされるからです。
「○○に効く」「○○の予防に効果的です」などの表現も禁止されており、使用した広告は薬機法66条の虚偽・誇大広告に該当します。
効果効能を示す表現をしないよう注意しましょう。
4.改善する
「改善」の表現は、症状や問題の改善効果が人によって異なるため、誤解を招く表現として規制されています。
たとえば「○○の症状を改善できます」「○○のトラブルが改善される」といった表現は、誇大広告と見なされる可能性があります。
ただし例外として、厚生労働省に認可された有効成分が含まれる医薬部外品では「シワを改善する」など、承認範囲内での表現は使用可能です。
一般的な化粧品や健康食品では、改善効果を謳うことはできません。
「○○が良くなる」「症状の改善が期待できる」といった間接的な表現も避けるべきです。
承認された範囲を超える改善効果の表示は、薬機法違反となる可能性があります。
薬機法違反にならないNGワードの言い換え

薬機法に抵触するNGワードも適切な表現に言い換えると広告に使える場合もあります。
化粧品と健康食品それぞれの具体的な言い換え例を紹介しましょう。
化粧品の場合
化粧品では厚生労働省が定めた56の効能効果の範囲内で表現する必要があり、医薬品的な効果を示す言葉は適切に言い換えなければなりません。
以下が具体的な言い換え例です。
保証や最上級表現を避けた言い回し、正確な範囲を示すことが重要です。
健康食品・サプリメントの場合
健康食品・サプリメントは医薬品と誤認させない表現への言い換えが必要で、体の機能改善や疾病に関する直接的な表現は避けてください。
間接的な表現を使うことや医薬品的な用法用量の指示を避ける、抽象的で健康維持の範囲内での表現への変更が必要です。
薬機法でNGワードを避けるコツ3選
薬機法違反のリスクを減らすため、実践的な3つのコツを紹介します。
これから紹介するコツを使えば法令を遵守しつつ、商品をPRできます。
1.効果効能を断定しない
効果効能を断定する表現は薬機法違反の最大のリスク要因であり、絶対に避けなければなりません。
「シミが消える」「ニキビが治る」といった断定表現は、医薬品的な効果を保証すると見なされ、重い処罰の対象です。
代わりに「肌に潤いを与える」「乾燥による小じわを目立たなくする」のように、製品が与える状態の説明や使用感の範囲に留めることが重要です。
「改善する」を「整える」に、「効果がある」を「サポートする」に変更するなど、マイルドな表現への言い換えを心がけましょう。
断定を避けることで、消費者に誤解を与えることなく商品の魅力を伝えられます。
効果を保証しない表現は薬機法を守る上での基本原則です。
2.最大級や強力、絶対などの強調表現を避ける
「日本一」「最高峰」「絶対」「必ず」といった最上級や絶対的な表現は、薬機法と景品表示法の両方で制限されています。
強調表現を使用する場合は、第三者機関による客観的な調査データと調査期間の明記が必須となり、根拠がなければ誇大広告と判定されます。
「最高の効果」は「こだわりの成分配合」、「絶対安全」は「肌へのやさしさを考えた設計」のように表現を和らげるのがコツです。
「完全」「100%」「究極」などの強調表現も同様に避け、「徹底的に」「しっかりと」といった程度を示す表現に変更しましょう。
強調表現の代わりに具体的な特徴や成分を説明すれば、法令違反を避けられます。
3.誤解を招く表現を避ける
消費者に事実と異なる期待を抱かせる表現は、薬機法違反です。
「誰でも安全」「全ての人に効く」といった不特定多数への効果保証や、「わずか○週間で効果が」のような短期間での変化を示す表現は避けなければなりません。
また、写真やイラスト、グラフによる暗示的な表現も規制対象となるため注意が必要です。
誤解を防ぐには「デスクワーク中心で○○が気になる方へ」のように具体的なターゲットに限定しましょう。
「○○と考えられています」「○○という報告もあります」といった客観的な表現を使用するのも手です。
口コミや体験談を掲載する際は「※個人の感想であり、効果を保証するものではありません」の注釈を必ず明記し、誤解のない広告表現を心がけることが重要です。
まとめ|NGワードを意識して薬機法違反を避けよう
薬機法は医薬品や化粧品などの安全性を確保し、健康被害を防ぐための重要な法律です。
違反すると刑事罰、行政処分、課徴金と3つの重い罰則が科され、企業の社会的信用にも深刻な影響を及ぼします。
特に「安心・安全」「治る」「効果」「改善」の4つは代表的なNGワードであり、避ける必要があります。
化粧品では56の効能効果の範囲内、健康食品では医薬品と誤認させない表現への言い換えが必要です。
効果効能を断定しない、最上級表現を避ける、誤解を招く表現を使わない、3つのコツを実践することで、薬機法違反のリスクを減らせます。
適切な表現を意識し薬機法を守った広告運用を心がけましょう。